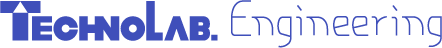今一番騒がれている3Dプリンターが一番得意とするのが、このプロセスです。
3Dプリンターが魔法の杖のように何でも出来ると言われかねない風潮ですが、3Dプリンターを動かすためには第一章でお話したようなCADを使った「設計」までが完了していなければなりません。
将来(それが近いか遠いかは分かりませんが)、この「設計」が半自動化して簡単になる可能性はありますが、現時点ではまだ設計は製品開発をする方自身が行わなくてはなりません。
正直、ちょっと大変だと思います。
だからこそ、そうして苦労した設計が終わると、それをカタチにして見た時の感慨はひとしおです。
3DプリンターはこうしたCADデータをカタチに変えるという点に関して、素晴らしい装置だと言えます。この章では、これら3Dプリンターを使ったモノ作りを中心に解説します。
さまざまな試作方法
3Dプリンターと一まとめに言われていますが、その中にも様々な方法があるのをご存知でしょうか?そしてそれぞれに得手不得手があることも。
ここではそのような様々な種類の3Dプリンターを使った方法の長所と短所を紹介します。あわせて、3Dプリンター以外の試作手法でも優れている手法を紹介します。
ちなみに広義に3Dプリンターと呼ばれている機械は、厳密には積層造形装置と呼ばれています。薄くスライスした「層」を「積み」上げて立体的な形状を作る装置、という意味です。
積層造形装置には、積み上げの仕方やそれに使用する素材の違いから、以下のような種類があります。
ご存知でしたでしょうか? そして上記それぞれの方法に得手不得手があるので、一口に3Dプリンターといっても注意して使わなくてはいけませんね。
|
どの試作方法を選択するか
それでは上述の試作手法のうち、果たしてどの方法が最も望ましいのでしょうか?
詳しくは次の項でそれぞれの試作方法を解説しますから、それも参考にして頂きたいのですが、まずはケースに応じてどの方法を選ぶべきかをまとめてみました。
①展示会などに出品したい(飾り目的)
このような場合には、速く・安く作れてソコソコキレイな光造形が最有力です。
磨いて塗装すれば、外観上は量産の製品と較べて遜色ない試作品を作ることが出来ます。 さらに微細な形状が必要ならば3Dプリンター(狭義)も有望です。 ただ3Dプリンター(狭義)は素材が柔らかく変形し易いので、展示会に出すとしても一回限りと割り切った方が良いでしょう。
これらの方法は1個だけ安く作ることが出来るので、展示会などの反応をみて設計修正することが出来ます。
もし展示サンプルが多く必要な場合には、最初の光造形見本を真空注型でコピーするという方法がお勧めです。 この方法は若干初期費用がかかりますが、10個~50個くらい作るのであれば他の方法よりは一個あたりの単価が安くなるためです。
②顧客に渡して評価をしてもらいたい
このような場合には、「壊れない」ことが必要になります。
3Dプリンター(広義)による試作製品は、結構壊れやすいのですが、ユーザーは中々そこに配慮してくれませんから。
通常我々が日常使うプラスチック材料にかなり近い材質を選ぶことが出来、かつ寸法精度も高く作ることの出来る機械加工による試作が一番望ましい方法です。
ただこの方法は3Dプリンター(広義)による試作と比べると、製造コストが高くなります。そこで、ナイロン造形による試作も考慮できます。
この造形方法は材料の強度はかなりあるので、大抵の稼動試験をすることができるのです。 そして機械加工よりずっと安くなることが多いです。
ただし、見た目が汚くなってしまいますが、また本当に動きの検証だけをするということが前提です。 また先ほど説明した、真空注型で作ったコピーを作るという方法も、数を作るのであればお薦めします。多くの3Dプリンター(広義)よりは壊れにくい素材を使うことが出来るので。
③店頭に並べて販促サンプルとしたい/小量製作して、実際に販売したい
このような場合には、残念ながら3Dプリンター(広義)による方法は使えません。
現時点で積層造形法に使われる素材は、我々が日常生活で普通に使うにはあまりに弱いのです。
ですから若干の初期費用をかけて簡易型を使った試作をしなくてはなりません。
簡易型の種類は製造する数量にもよりますが、100個前後であれば樹脂型、それ以上であればカセット型やアルミ型などになることでしょう。
|
|
|