顧客の期待を裏切ることで200点を取れる可能性が見えてくる
テクノラボの技術ベースは林と大島が二人で作った会社です。会社の価値観は二人の価値観の融合点にあり、それが会社の付加価値だと思っています。テクノラボのすべての価値基準はここに起因します。
大島と働き始めて少しした頃のエピソードに遡ります。
テクノラボは大島のデザインスキルによって、単なる金型ブローカーではなくて製品のデザイン/設計から顧客の相談を請ける会社となることができました。
林と大島で客先の話を聞き、それを元に大島がデザインを描くことが増えましたが、彼は時に顧客の依頼を無視してデザインを進めることがありました。
要望されたものと出来たものが全然違う。丸っこい感じでって言われたのにカチカチのスクエア形状とか、壁掛けって言われたのに置き型になっていたり。
私はそれまで顧客に言われたとおりに作るべきという常識に縛られていましたから、困りました。
約束した納期=提出する直前で、顧客の要望とは全然違うデザインしかない(と少なくとも当時の私には思えてしまった)ことが何回かありました。
でも、中には怒り出す人もいるんですが、多数の客はそれを物凄く喜んでくれるんです。そんなふうに考えなかったなぁ、って。打合わせで取り繕うのにハラハラしていたことの多くは杞憂でした。
林は客のいうことを如何に丁寧に聞いて、その通りに仕上げるかしか考えていなかったけれど、そうして徹底的に努力し続けても、100点にはならない。
でも大島が作るデザインは、たまに怒り出す(0点)人もいるけれど、絶賛される(200点)こともしょっちゅうなんですね。
それが相手の期待を裏切ることで、100点を簡単に超えることもある。これは衝撃でした。
考えたら当たり前ですよね。プロとして求められている以上、答えは本来こちらが呈示すべきで、客に聞くべきではなかったのです。それからもう一つ、プロが欲しいものを素人に見せるんだから、それは元の要望より良いのです。
大島は客の話を聞いて、客が売れるだろうと思っているものは作らずに、自分が欲しいものを作っていたのです。これこそが付加価値なんだと、目から鱗が落ちた思いでした。
もし林が自分のやり方にこだわって、大島のやり方を否定していたら、テクノラボはきっと死ぬほどつまらない下請でありつづけただろうな、と本当に頭が上がらないエピソードです。
これがテクノラボが持っている価値観の一つです。
それからもう一つ、だからこそ多様性は大事なのだと思っています。
違う価値観が融合するからこそ、付加価値が生まれるわけです。
同じ国籍、学歴、家庭環境の人が集まる組織は、居心地は良いかも知れないけれどきっと新しい価値観は生まれないだろう、と思います。
同じルールを社員に課して、社内の同質性を保とうとする会社も多いのですが、テクノラボはその逆が企業に取って望ましいことだと考えています。
さらに言えば、才能というものを定義するのがとても難しいとも感じています。
大島も林も、出来ないことがとても多い。
だから言い訳するわけではないのですが、できない我々が集まって色々なことができるようになっていることを考えると、才能というのは不思議なものだと感じました。
組織の一部として自分は何ができないか認めるということ
実は会社組織として考える時、才能ある人材とは何でもできる人ではなくて、むしろ自分がは何ができないかを知っている人なんじゃないだろうか、と今は考えています。
何かができない人は出来ることの価値を正しく評価できるし、大して価値が認められない無駄なサービスに努力することもなくなるのではないかと考えたからです。
何かができない以上、限られた出来ることを磨かざるをえないので、それこそが才能だと思うようになりました。自分を振り返って考えると何でも出来た、と思っていた時には、実は、何にも生み出していなかった、と思います。反省ばかりです。
変な価値観ですかね?
会社は一定の成果を顧客に出し続けなくてはいけないからこそ、出来ないことを知ってそれを出来る企業に任せれば良い。そうすれば逆に自分が一番得意なこと、一番付加価値が高いことが社内に残るはずだと考えています。結果として一番得意な所で仕事をすることは才能と呼べないだろうかと思っているのです。
こうした考え方を、一緒に働く人たちに常に押し付けるのが、社長の林の仕事なのではないかと思っています。
だからこれが社風の基盤(になるといいな)と考えています。







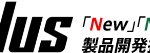

[…] <創業ストーリー3へ続く> […]